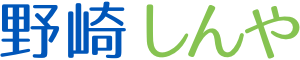視察の日程 令和4年10月12日から10月14日
視察場所 長崎県長崎市 出島メッセ長崎
テーマ 個性を活かして選ばれるまちづくり
長崎市で開催された第84回全国都市問題会議に清風クラブ8名で研修に行ってきました。テーマは「選ばれる」まちづくり、何度も訪れたい場所になるために、全国から2000名を超える市長や市議会議員が来られました。人口減少の中で各自治体も生き残りに必死で様々な施策を展開し、持続可能なまちを目指しています。魅力ある地域資源に気づき、磨き、生み出していく、それが移住や転入につながります。一人一人が平塚を愛し、平塚を好きになりましょう。そして他者に平塚を推奨できるよう、平塚に誇りと愛着を持ちたいと強く感じました。
第1日は、ジャパネットホールディングスの高田社長が基調講演を行い、その後、長崎市長田上氏、島根県立大学地域政策学部准教授田中氏、山形市長佐藤氏、地域力創造デザインセンター代表理事高尾氏など4名の方がテーマに沿った報告をされました。二日目はパネルディスカッションが行われました。
一番印象に残ったのは、高田社長と景観専門監高尾氏の話でした。
「高田社長の内容」 民間主導の地域創生の重要性を述べる
長崎のプロサッカークラブ「V・ファーレン長崎」の運営や長崎スタジアムシティプログラムを通じて、見つける、磨く、日本中に伝える、そうした視点で、行政と民間の官民、そしてそこに住む地域住民の方々と連携し長崎市を始め全体の幸福の熱量を増やすことに力点を置いています。従って社員の働き方改革も推進しています。
高田式改革は、会議を禁止する時間を設定するノー会議タイムの導入、集中ルームの導入など大変ユニークです。他にも週3回のノー残業デー、時間外勤務制限など残業時間の見直し、スーパーリフレッシュ休暇など休日の改革、育児時差出勤制度の拡大、などにより働き方を変えて、会社の労働生産性や離職率の向上に役立てています。
また、企業の役割は幸福の最大化と考え、健康経営にも取り組んでいます。私は議会で本市も市内の企業に健康経営に取り組んでもらう仕組みを考えたらと2回提案しましたが、実現に至っていません。高田社長は、社員の健康は宝として、最大の幸福を考え、社員一丸となって地域創生に取りくまれているのは大変すばらしいと感じました。平塚市もこの事例を参考に起業に働きかけるべきです。
「長崎市長の報告」まちの価値を見つけ、価値に気づき、磨き、生み出す
長崎市の状況
総面積は約406k㎡、人口は約40万人の中核都市。長崎港を中心としたすり鉢状の地形で形成された斜面市街地と相まって独特な都市景観をしています。
そのため、自転車は市内にほとんどなく、本市の自転車のまちづくりとは異なる。
長崎観光の視点も歩きながら新たな価値を見つけ、その価値に気づく取り組みをしています。「長崎さるく」は全国のまち歩き観光の先駆けで、「さるく」はぶらぶら歩くという方言で、市内にちらばっている魅力を見つけながら歩くものです。
暮らすひとにとり身近でも、気づいていない価値に気づくことでまちへの愛着につながります。
価値を磨くために、長崎市は全国でもまれな、「景観専門監制度」を導入。
職員の景観に対する意識の醸成と公共デザインの指導と管理が仕事ですが、長崎駅周辺の再整備事業や市内各地の公園、道路、建物などの整備・改修をすすめています。景観専門監は、狭義の行政業務上の景観だけでなく、個々の公共事業によってまちに価値を創造する事を使命としている。快適性や場所の魅力を伝え、暮らす人や訪れる人に大切なもので、まちの魅力の向上につながると思います。
「長崎市景観専門監の取り組み」 地域力創造デザインセンター代表理事 高尾氏
約9年半にわたり、長崎駅周辺整備、出島メッセ長崎、新庁舎、出島橋・公園、まちなか夜間景観整備、展望台など100を超える事業を監修。地域の価値創造を目指す行政組織はどうあるべきか。3点を提言された。
事業の縦割りの問題
個々の事業目的の最大化や最適化が積み重ねられ全体として良いまちにならない。
利用者目線でまち全体を意識した事業の検討が必要で、そのためのデザイン監修や事業間調整を行う主体が事業現場に必要です。
時間に関する問題
事業のビジョン作成から現場施工、デザイン調整まで、一貫して関わる職員はいない。微調整を積み重ねる地道なデザイン調整は全体の質の向上に大きく貢献する。
人材の育成
職員は繁忙のあまり、往々にして価値を想像し、想像する意識が欠落している。
景観専門監は、職員に問いかけをしながら、地域の歴史、場所の履歴、周囲に見えるもの、地域住民の願い、利用者のニーズ、市全体のビジョンなど相対的に読み解き、あるべき整備の姿を検討していく。そのため「問う」存在が必要。
人口減少の中で、市民の暮らしと経済を支える新しい産業を確立し、交流の産業化を進めていくうえで、本市でもこのような景観専門監を導入して駅前の再整備や海の公園整備に活かせたらと思いますが、市長に要望をいたします。