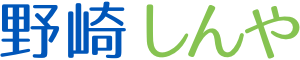100年時代の人生戦略
2025年は団塊世代が全員、後期高齢者になり、2040年には高齢者人口がほぼピークを迎えます。人生100年時代に向けて直面する様々な課題に取り組み、健康で元気に豊かな老後を一人一人が地域で幸せに暮らせる事を念頭に、まず、住民税非課税世帯等への給付について、2023年から今年の春まで給付を実施したが、一人でも多くの方に給付が行き渡るようどのように工夫されたのか伺います。
一人暮らしの高齢者に寄り添う環境づくり
少子高齢化が進めば、9年後の2033年頃には、世帯人口で2を割り、1世帯一人の時代になり、地域の支えあいがより必要となります。一人暮らしの高齢者の想いにどうよりそうか、本市の考え方、取り組みについて、以下お聞きします。
- 高齢者の日常生活を支えるため、介護保険サービス以外の民間サービス、例えば配食、掃除・通院などの代行サービスを利用しやすくする取り組みを事業者との連携でどう進めていくのか。本市の見解を伺います。
- 令和6年度の施政方針では、町内福祉村の新規開設促進とありますが、町内福祉村の役割や開設促進に向けた今後の考え方や取組について伺います。
- 高齢者よろず相談センターの役割、相談の件数や内容についてお聞きします。また、新たに基幹型地域包括支援センターを設置しますが、目的、期待されることは何か、伺います。
- 高年齢者雇用安定法は、3年前に改正され、70才までの雇用機会の確保が努力義務になりました。そこでシニア世代が活躍しやすい働く環境づくりが必要です。人手不足が続く中、企業では多様な人材に活躍してもらうために定年の延長や廃止、再雇用者の処遇改善などの動きがありますが、高齢者の雇用を促進させていくために市はどのように企業や高齢者に働きかけていくのか見解を伺います。
- 生きがい事業団と市の産業施策の連携に向けた取り組みを伺います。
介護離職防止に向けて
5月24日改正育児・介護休業法が成立し、令和7年4月より介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務等になりますが、介護離職の状況や防止対策について以下伺います。
- 在宅で介護をしている方で介護を目的として離職をした人の状況を把握しておく必要があると思いますが、現状を伺います。
- 介護サービス事業所の経営状況が悪化した場合、十分なサービス提供がなされず、在宅で介護をしている家族の負担はより重くなり、会社を辞めざるをえなくなります。訪問介護事業所の経営状態を把握しておく必要があると考えますが、現状を伺います。
健康寿命の延伸、介護予防の取り組み
健康長寿を実現するために大切な3つの要素は栄養、社会参加、運動です。特に運動としてウオーキングや体操があります。以下伺います。
健康体操
健康体操はいつでも、だれもが、参加して楽しめるように地区公民館等を利用して多くの体操が行われています。そして、高齢者の認知対策や、腰痛防止、転倒防止など介護予防につながるような効果があります。また、くすのき体操を市の体操としていますが、利用状況や課題、今後の進め方、ほかの健康体操の紹介などについて伺います。
ウオーキングアプリの導入
歩行の行動を促すために利用状況に応じてポイントを付与、楽しみながらポイントがたまり、そして抽選で賞品が当たる、この健康ポイントを専用アプリのスマホを活用して健康になり、歩くことでまちの新たな価値や魅力の発見にもつながるまちづくりを提案したい。川崎市では、利用者が歩いた歩数が小学校などへの応援金になる仕組みで利用者にも抽選で協賛企業から提供される商品券などが抽選で当たる新たな取り組みをしています。横浜市や鎌倉市、藤沢市、小田原市等県内自治体でも多く導入されています。本市の見解を伺います。
地域公共交通の推進
自動運転バスの実験
自動運転バスの運行を見据えた駅南口ロータリーの改修設計にかかる経費が今議会補正予算に土木費で計上されています。補正予算の内容や駅南口広場、特に駐輪場や噴水広場などは、どのように整備されるのか伺います。
地域公共交通網計画の実施に向けて
市内各地区の交通不便地域の課題を整理して、路線バスを補完する交通として新たにコミュニティ交通の導入を検討していますが、進捗状況を伺います。
出会いのまち平塚へ
結婚を望む方への支援
異次元の少子化対策、待ったなしです。総合計画にある少子化対策として結婚を望む方への支援が明記されています。以下伺います。
合計特殊出生率は去年、1.20となり、8年連続の減少で過去最低を更新しました。最も低かったのは東京都で初めて1を下回りました。去年1年間で生まれた子どもの数は前の年から4万人あまり減って約72万7000人でした。婚姻の件数は47万4717組、戦後初めて50万組を下回りました。
- 本市の出生数と婚姻数の推移、10年前、直近の状況について伺います。
- 本市は9年連続で社会増加ですが、その期間に20歳代の女性の社会増減の状況から見える課題は何か。具体的な対策をどう考えていますか。
- 若者への経済支援も必要です。非正規から正規社員への格上げや賃金アップなどの経済的支援をどのように考えているのか伺います。
- 本市では、若者に対する奨学金の返済支援を5月20日から受け付けましたが、補助対象や人数などの内容について伺います。
- 結婚後の住まいの確保も必要です。空き家の改修費用等への補助など空き家の活用について伺います。又、本市の空き家の現状についても伺います。
- 国の結婚新生活支援の「地域少子化対策重点推進交付金」の活用はされたのでしょうか。活用してなければ理由と今後の活用の考え方を伺います。
- 七夕まつりの縁結びパーティーについて、今年の七夕まつりの7月7日に縁結びパーティーを企画している大手結婚相談所の団体の方がいます。また人工知能(AI)マッチィングを活用する自治体も増えています。未婚化や晩婚化に、相手探しの選択肢を増やすため有効と考えますが、本市の見解を伺います。さらに来年度の七夕実行委員会で婚活について議論いただき、七夕イベント部会の中に新たに婚活部会をつくるべきと考えますが、七夕まつりの事務局としての市の見解を伺います。
子どもまんなか社会に向けて
昨年、こども家庭庁が発足しましたが、子どもたちが社会の中で何をやりたいのか、どうしてほしいのかなど、すべての子どもが幸せに暮らせる環境づくりが求められています。以下伺います。
子どもが主役のまちづくり
昨年の菫平自治会の盆踊り大会で子どもたちのアイデアと行動力で「夜市のこども屋台」が大盛況で市からみんなのまちづくり年間大賞で表彰され、港地区でも小学生が地元産シイラの販売を積極的におこない、大きな貢献をしました。このように子どもたちの発想と行動力を地域社会の中で活かすために、本市ではこれから子どもたちの意見や要望をどうくみ上げていくのか、について伺います。
びわ青少年の家の活性化
令和6年の施政方針の中でびわ青少年の家の利用対象を広げ、幅広い用途で利用できるようにするとしていますが、具体的に何をどうするのでしょうか、構想について伺います。現状の利用者数、利用者の声、今までの修繕費の内容について
地球温暖化による世界的な異常気象に備えて
中国やブラジルの洪水、アメリカの竜巻、世界中で山火事、インドやフイリピンの熱波、北極の氷が解け始めているなど地球崩壊の前兆とも言えます。そして日本の夏はラニーニャ現象でさらに暑くなると言われています。地球温暖化による海水温度上昇により豪雨や大雨、大型台風の到来への備えが重要になってきます。5月下旬の台風第1号では台風が梅雨前線を刺激して線状降水帯が発生し、警報級の大雨が発生した地域もあり、過去の経験則では測れない状況です。以下伺います
金目川水系の流域治水による河川整備
県が進めている金目川水系の河川整備の進捗状況と今後の進め方について、伺います。
平塚市総合浸水対策第3次実施計画
本市では、令和6年3月に平塚市総合浸水対策基本計画の実施計画として令和6年度から令和10年度までを計画期間とする平塚市総合浸水対策第3次実施計画を策定されましたが、策定の目的とこれまで実施してきた取り組みをどのように検証したのか、また策定にあたり、新たに踏まえた視点と今回の重点対策地区の取り組み内容について、伺います。
水防団の消防への移行から見えてきた課題
水防団が解散して消防に移行し2年が経過します。令和4年4月に河川巡視マニュアルが作成され訓練等をおこなってきましたが、これまでの取り組み内容と今後の異常気象を想定し、河川流域の住民の安心・安全体制に向けてどのように取り組むのか、課題も含めて伺います。また、過去の水防団の出動回数を伺います。
多文化共生社会のまちづくり
市長表敬訪問として5月に西湘日韓親善協会、6月には台湾ロータリークラブの方々が来られ、7月の七夕ではブラジルやカウナス市の七夕飾りが彩を添えます。秋には国際交流フェスティバルも開催されます。又、本市はカンボジア難民を受け入れた自治体です。海外の姉妹都市、アメリカのローレンス市から7月に、青少年がリトアニアのカウナス市からは10月、公式訪問団が本市に来訪されます。いま、国際交流が熱いまち平塚になっています、以下伺います。
- 外国籍の国別人口推移について
- 庁舎1階に外国籍の市民相談窓口が設置されていますが、設置の目的、利用状況、相談内容について
- 言葉や社会生活、子育て、教育など多岐に渡る相談に対しどのような庁内体制で対応しているのか
- 秋開催される国際交流フェスティバルの内容をはじめとした本市の多文化共生社会の実現に向けた取り組みについて伺います。